
「うすはり」とは
「うすはり」の「はり(玻璃)」とは、ガラスを意味する言葉です。
名前の通り、薄いガラスで作られたこのグラスは、大正11年創業の松徳硝子が生み出した逸品です。
代々受け継いだ電球用ガラスの製造で培ってきた職人の技術が、厚さ0.9mm、通常のグラスの半分以下という、極限の薄さの実現を可能にしました。
うすはりグラスは、全て職人の手によって一つ一つ丹精込めて作られています。
この繊細な飲み口が味を引き出し、氷の音、手にした感触に独特の味わいを醸しだします。
実際に手に取るとあまりの頼りなさに驚きますが、薄い分だけしなやかで衝撃に強く、特に割れやすいということはありません。
ニューヨークのインターナショナルギフトショーで「ベストニュープロダクト賞」を受賞、またこの薄硝子制作の製法は「江戸硝子」として東京都の伝統工芸品指定を受けています。
「うすはりグラス」ができるまで

粉末状のガラスに加えて、カレットと呼ばれるガラスの不要な部分も再利用します。「2」で紹介する窯に原料を入れ溶かしておきます。

工場の中央に窯(画像右)があり、温度は約1,300〜1,350度に保たれ、窯は365日火が消えることは窯全体を換える時以外ありません。中で溶けたガラスの原料を竿で巻き取り小さい玉(下玉)を吹きます。

下玉の上に、もう一度必要な量の種を巻き手早く形を整え、型に入れ回しながら息を吹き生成。これらは迅速かつ正確な作業が要求される。

型に吹き込んで作られたグラスは、まだ熱をもっているうちに木片をあてながら回転させ形の微調整を行います。

熱の変化に弱く、そのままにしておくと割れてしまうため、平均535度の徐冷炉に入れゆっくり冷まします。ベルトコンベアで運ばれてた製品の傷や汚れなどのチェックを行ないます。

ダイヤモンドの刃で傷を入れ、バーナーで熱し、余分な部分を手によって切り離します(火切り)。

金剛砂と水を混ぜ落とした平板にて「平摺り」を行い、ザラザラの切り口を平らにします。

切り口に火をあて切り口を滑らかにし(口焼き)、最後の検品を行い、出荷されます。
お取り扱い上のご注意
最初のご使用時は中性洗剤で洗って下さい。
普段の使用後も中性洗剤でOKです。
ガラスを傷つける恐れのある研磨剤入りスポンジや金属たわし、クレンザー等を使用しますと、破損の原因になります。
割れにくいといっても、やはりガラスです。
特にグラスの内面を洗う際は、力を入れてひねり洗いをしますと破損し、思わぬケガをまねくおそれがありますのでご注意下さい。
柄付きスポンジのご使用をおすすめします。
急激な温度変化(特に急冷)で割れる事があります。
グラスが熱いうちに冷たい物を入れたり、濡れたところに置かないようご注意下さい。
ガラス表面に傷が付くと破損しやすくなります。ガラス同士あるいは硬いものとぶつけないようにお気をつけ下さい。
グラスを積み重ねますと、破損したり、外れなくなる恐れがあります。
スタック専用の商品以外は、積み重ねないようにして下さい。
セミクリスタルガラスは、耐熱ガラス、強化硝子ではありません。大切にお使い下さい。
手作りのため、形に若干のばらつきが出たり、製法上やむをえず小さな気泡などが混入する事がございますが、品質に問題はございません。予めご了承くださいませ。
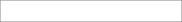
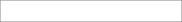
 Myページ
Myページ ログアウト
ログアウト 新規会員登録
新規会員登録 ログイン
ログイン カートを見る
カートを見る はじめてのお客様へ
はじめてのお客様へ



